About 京人形とは
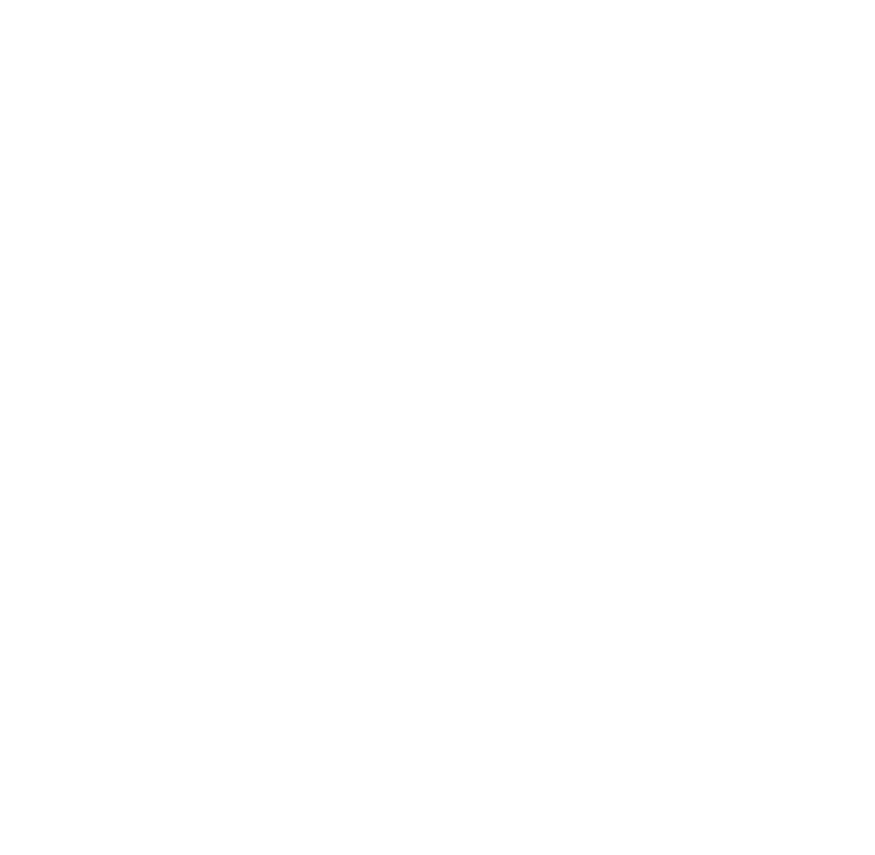

それぞれの技法
- 木彫胡粉地上げ
- 仏師の余技とされる人形制作は、木彫で原型を作り、形成された原型にねった胡粉を塗り重ねて、磨きあげて仕上げていきます。
- つくね
- 一つの型から大量に造る技法として、桐材の粉と布海苔を合わせ、粘土状にしたものを木型に押し込んで型をとる方法です。これは雛人形の頭や、「居狂い」のような小さなものに用いられています。
- 張り抜き
- 木彫の頭の原型の上から薄い和紙を何十回と張り合わせた後から、和紙を切開いて木型をぬき、再度薄紙を張り合わせて原型を成形する方法です。この技法は今日ではおこなわれることはなくなりましたが、面庄家に残る資料からは、当時の技術の冴えがうかがえます。この技法は、量産することを目的したものです。
信仰の対象
鑑賞の対象

御所人形
御所人形は、「お土産人形」、「白菊」「白(しろ)肉(じし)」、「頭(ず)大(だい)」、「三つ割り」「狂い」「立狂い」「居(い)狂(ぐるい)」とよばれていた胡粉仕上げの童子の人形を、明治の末に人形愛好家によって統一された総称です。十三世面屋庄三はその制作心情から、「三等身のプロポーションは、京人形師の生み出した究極のデフォルメである」と述べています。
玩具としての対象

三つ折れ人形
…人形の関節の部分、脚の付根と膝と足首が自由に折れ曲がるよう工夫されたものです。足だけでなく手も自由に動き、立ちもすれは座りもする。姿態に変化の多い御所人形がその自由さを求めて一歩前進したものだが、衣裳を着せ替えて、立たせたり座らせたりして女の子が遊ぶのに向いているので、この手法は御所人形よりは、愛玩用の衣裳風俗人形の方へ多く使われて発達しました。(市松人形は、これの簡便なもので、手足と胴を縫いぐるみでつなぐ。動かせるが一人立ちは出来ない。)

